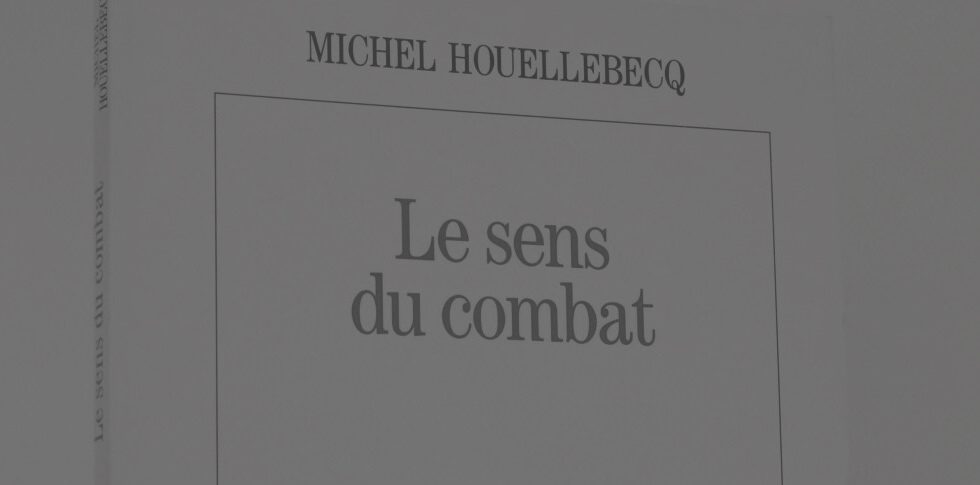試訳
僕を目に留め、彼女は腰を突き出した
そして皮肉っぽく言った、「来てくれて嬉しいこと……」
僕はぼんやりと彼女の胸のカーブを見た
そして帰った。僕の机は綺麗そのもの。
毎週金曜日の夕方、僕は書類を捨てて
月曜に自分の机がわかるようにしていた
僕は彼女が好きだった。哀れな女で、
醜いデブの秘書だった。
彼女はぼんやりとシュプタンヴィルのすぐ近くで暮らしていた
赤毛の一人っ子と、ビデオカセットと共に
彼女は街の噂話なぞ知らず
土曜の晩にはポルノ映画を借りていた。
手紙をタイプする、彼女の顔は好感が持てた、
彼女は一生懸命に従順であろうとしていたから
年齢は35かひょっとしたら50くらい、
死に向かってはいたけれど、彼女に歳など関係なかった。
正午
シュルクフ通りが延びている、雨降り——
遠くには、加工肉屋兼仕出し屋がある。
恋するアメリカ女がひとり
意中の人への手紙を書く。
人生が流れ去るのは少しずつ——
傘をさした人間が
探すのは出口の扉
パニックと退屈のあいだ
(泥のなかに踏み潰されたしけもく)。
低空を飛ぶ存在、
のろまに動くブルドーザー——
ぼくが生きたのは短い幕間
突然人のいなくなったカフェのなか。
ミニスカートの耐え難き再来
メトロでは、若い女たちが
劇のような雰囲気で行き交う
そんな五月、なんて扇情的なんだ。
ぼくは通学鞄を忘れて出てしまった。
「アヴァンチュール」の好機なのか。
誘惑についての知育ゲームなのか。
ぼくが過ごす日々は明らかな現実で、
唖然とだってしてしまう。
バラールとクレテイユ区間を走る8番線
鉛色の車両は果てしない。
翌日ぼくは倒れ込んだ
ある晴れた日のこと。
春が始まった
狂乱するミニスカートの力で、
ぼくにはもうたくさんの時間がなかった
(またぼくは自分の肉体が生き生きとするのを感じていた)。