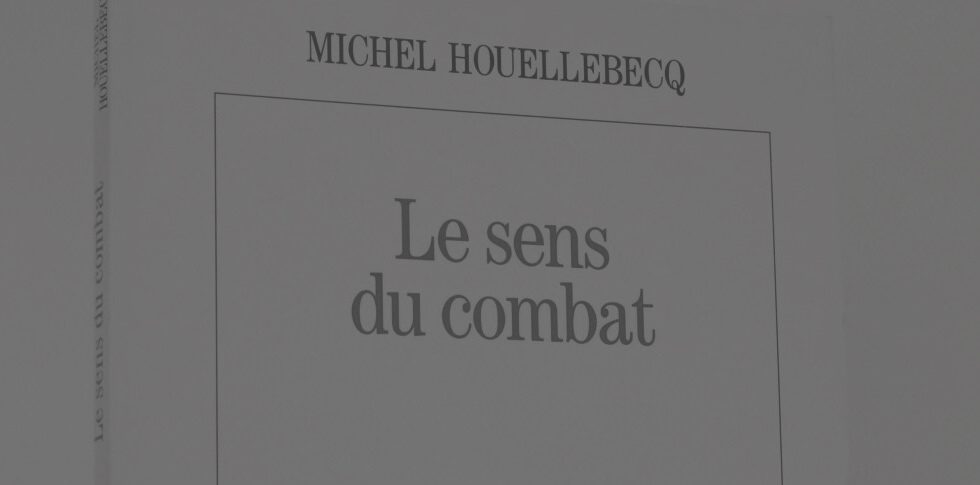試訳
ぼくは午後中ずっと歩いていた。
自然とふれあいながらの「スポーツ活動」というやつだった。
けれども、ぼくはまたもや不安でいっぱいだ。
ホテルは快適だ。
ホテル、そいつに何もケチをつけることはできない。
ぼくに重くのしかかるのは単純に生の存在で、
この存在が事実上ソワレを不可能にする。
ぼくらの幸せを決めるのは精神の存在あるいは不在で
ぼくが午後いっぱい自分の身体を鍛えたところで無駄で、夜が近くなると、ぼくの心になにかが重くのしかかり出す。
フォンタン・サオルジュの駅
(そこに人はおらず、閉まっていて、窓のガラスが割れ、トイレは詰まっている)
最終列車はもう通り過ぎてしまったに違いない。
ぼくはリュックサックからスワッピング向け出会い系雑誌を取り出し、
そいつを均等に二つに引き裂いた
それから「トルコ風」トイレの傍に塊をおいた。
女たちはディルドや黒ずんだ巨大なペニスを欲しがり続けるのだろう
イタリアの鉄道退職者のありえそうもない喜びを求めて
そいつは自分がキャリアを築き
学校が閉まってしまう前に
子どもたちを育て上げた鉄道を訪れに来たのだ。
地下鉄の中でも、外周道路でも、
機械は作動し始める
僕は立ち止まり、即座に耳を澄ます──
機械が爆発するのが聞こえる
ゆっくりと、まるで臓物のように、
まるで黒ずんだ脳室のように──
遠くにはGANタワーが見える、
そこで僕の人生が決まるのだ。
幹部たちは己が試練に向かって登っていく
ニッケル製のエレベーターのなか、
秘書たちが通り過ぎるのが見える
マスカラを直す秘書たちが。
家並みの下、通りの端に、
社会機械が前進している
未知の目標たちに向かって──
我々にはもはやチャンスはない。
向かいのホームにいるあの男はレースの終盤にいる——
ぼくはもう完全にスタート地点にいない。
どうしてぼくは彼に強く同情しているのか?
<正確な>、理由は?
ホームの、ぼくのそばに、恋人たちがいるのだが
その男には目もくれない
(嘘っぱちの恋人たちだ、だってヤツはすでに禿げているし)。
だけど、恋人たちは抱き合っている——
ふたりのあいだにひとつの世界が存在していると信じているようだ、
それはあの男の世界とは異なるもので、
正面にいるその男は
立ち上がって自分のプリスニックの袋を集めていて、
レースの終盤にいるのは確実だ——
彼はキリストが彼のために死んだことを知っているのか?
彼は立ち上がる、自分の袋を集める、
彼は足を引きずってホームの端までなんとか歩く
そこで、階段の傾きのせいで、
彼は消える。