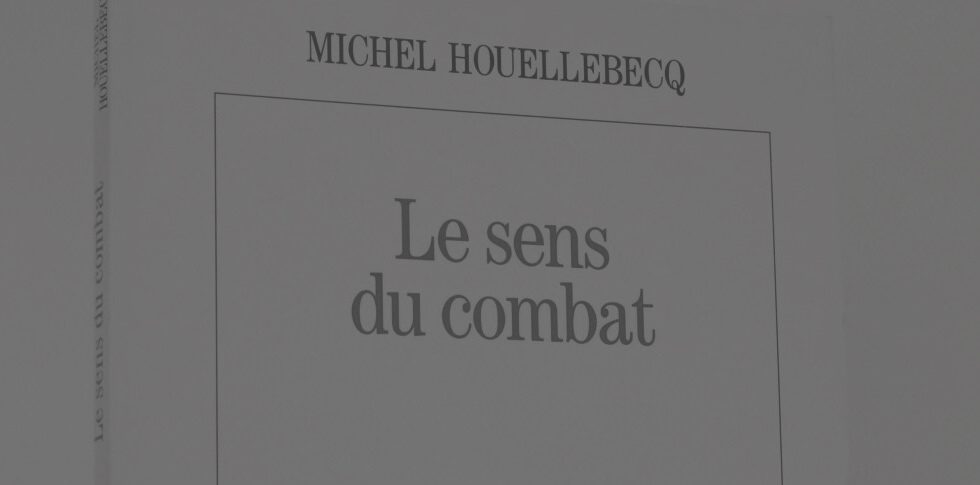試訳
血に身を捧げ
ぼくが本当に旅立つことはもうない
ぼくはこの場所を知っているから
それに自分の権利を知っているから、
そして怒りを経験したから。
人間に仕えて、
都市に安んじる、
ぼくは自分の部屋をよく知っている
夜の帳が下りるのを感じる。
天使たちが
壮麗なる天へと飛び去り
神と再会する、
女たちが笑っている。
自分の机から離れられず、
都市に安んじる、
緩慢な激しさ
無慈悲な夜の。
都市における夜、
緩慢な広大さ、
空に描かれる
きわめて残酷な光景
それは動き、痙攣し、赤い
形から切り離されたもの。
身を捧げるは血、
ほぼ意識されない不快感、
愛の残忍な終わり
現実のかけら——
これらすべては何をするためのもの?
ひとつの光景という考え
一曲の終わり
人間は絶望し
怒りを待つ
そして破裂した身体は
傷ついて、うずくまる
虐殺を期待しながら。
ぼくは糧を持っていくよ
最後の憎しみの糧を、
ぼくは自分の歯にこすらせ
悪を強く感じる。
ぼくは悪巧みに詳しい
押し潰された肉の悪巧み
騙していると言われるが、
ぼくは自分が正当だと感じている
人間の苦しみゆえに、
実現しなかった希望ゆえに
無益な日々が
密集して押し潰されるがゆえに。
ぼくは公平ではない、
だけどぼくは自分の部屋にいる
天使たちがぼくの手を掴む、
ぼくは夜の帳が下りるのを感じる。
断念する瞬間、ぼくはベンチに崩れ落ちる。しかしながら、欲求の機構がふたたび作動しはじめる。晩は嫌なもんだ——ひょっとすると平日も、ひょっとすると人生も——酒瓶を買いにまた外に出なければならないのは避け難い。
若いブルジョワ女たちがモノプリの棚のあいだをうろついている、雌ガチョウのように優雅にセクシーに。おそらく男どももいる——そんなこと知ったこっちゃない。自分とその他の人類とのあいだで言葉があり得ると考えないようにしても無駄だ、ヴァギナは入り口であり続ける。
ぼくはふたたび上階に向かう、ビニール袋に入れたぼくのラム酒の瓶を握って。ぼくは自分を壊している、それは自分でよく分かっている——ぼくの歯がぼろぼろに砕ける。どうして、これほどまでに、ぼくが見ると女たちは逃げていくのだ? ぼくの視線が、哀願しているとか、理性を失っているとか、怒っているとか、変態的だとか思われているのか? ぼくには分からない、おそらく決して分かることはないだろう——しかしそのことがぼくの人生を不幸にしているのだ。
晩の終わり
晩の終わりに、嫌悪感が強まるのは避け難い現象だ。恐ろしいことはすべてある種の計画表に書かれている。とはいえ、よくわからない──僕はそう感じる。
身体の内側の空虚が拡大する。そんな感じだ。起こりうるあらゆる出来事から剥がされている。君はまるで空虚のなかに吊るされているかのようだ、あらゆる現実の行動から等距離に、怪物的な力の磁力によって。
こんなふうに宙吊りになって、世界を具体的に捉えることができないと、夜は長く感じられることだろう。実際、長くなるはずだ。
しかしながら、それは守られた夜だ──でも君はこんな保護を好まない。少し経てば、町に戻ったり、日常に戻ったり、世界に戻ったりするたびに、この保護のありがたみがわかるだろう。
9時になると、世界はその十全な活動をもう始めているだろう。世界は軽やかに廻るだろう、軽い唸りを響かせながら。君は参加せねば、身を投じねばならないだろう──出発前の揺れる電車のステップに飛び乗るようなものだ。
君はうまくできないだろう。今一度、君は夜を待つだろう──夜はしかしながら、今一度、君に枯渇と不確かさ、そして恐怖をもたらすだろう。かくしてこんな光景が、来る日も来る日も、世界の最後の日まで繰り返されるだろう。
歯の裏側から喉奥にかけて、僕の口蓋を覆い尽くす茶色く、硬く、絡み合う分岐網はさながら死んだ枝木のよう──しかし、その内奥では痛覚神経が生きている。そのぎざぎざと分岐していくそのバラバラの模様はひどく生命力が強く、茎たちが形作る鬱蒼とした茂みはまるで肉の上の少々ざらついた表面のようだ──これら弱々しい茎たちがのしかかる枯れ枝の束の重さをかろうじて支えている。この下方の表皮は汚く、巨大な汚れの塊が付着していて、空き瓶、キャップが転がっては茎にぶつかり、痛みによる震えでできた花壇全体をこの茂みが占めている。イカの骨まである──分岐網はその周囲で成長し、固くなって硬化したのだ。
誰かが金属製の櫛を持ってやってきて、この茂みを梳かしはじめるのが僕は怖い。全体は音を立てて裂け、締まりのない噴出とともに僕の口内から根こそがれるだろう──僕の歯の根も一緒に、全部が根こそがれ僕の口からぶら下がるのだ、筋張った血塗れの肉の塊のように。