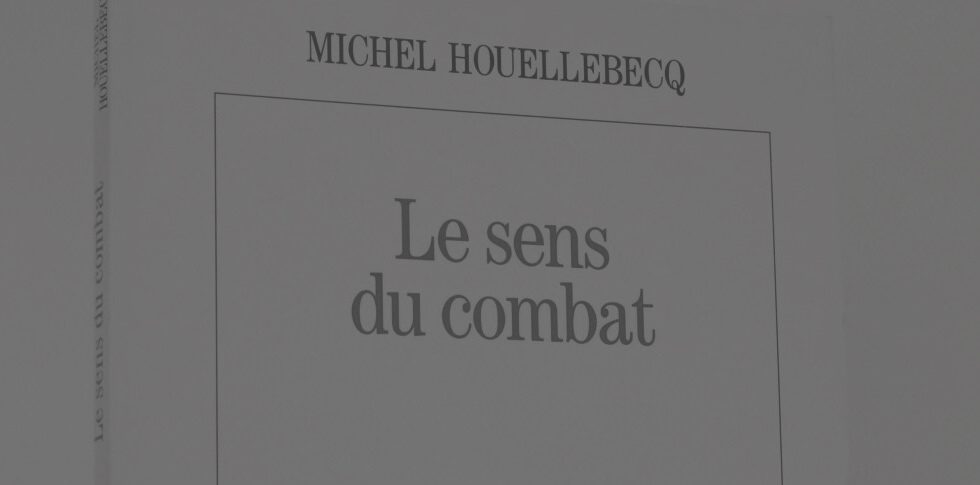試訳
風景の崇高な抽象化。
<クルトネからオーセール北>。
ぼくたちはモルヴァン山地の支脈に近付いていく。不動、車内部における、は完璧だ。ベアトリスがぼくの隣にいる。「良い車」と彼女はぼくに言う。
街灯が奇妙な姿勢で傾いている——祈っているかのようだ。なんにせよ、街灯が黄橙の弱い光を発しはじめる。「ナトリウムの線スペクトル」とベアトリスが言い切る。
もう、アヴァロンが見えている。
良い天気だった——ぼくは乾いた黄色い丘に沿って歩いていた。
植物たちの不規則な乾いた呼吸、夏だ……植物たちは死ぬ準備ができているかのよう。虫たちは羽音を鳴らし、白い空という不穏で固定された天蓋を突き破る。
しばらくすると、陽射しのなかを歩いているんだ、夏に、わけの分からないという感覚が大きくなり、我が物顔で空間に広がり、いたるところでその感覚が見出される。たとえ出発の際に目指す先があったとしても(それは本当にめったにないことだ……ほとんどの時間、ひとは「散歩」にかかずらっている)、目的となるそのイメージは消え失せる、そのイメージは熱すぎる空気のなか蒸発するかのよう、きみたちが固定された無慈悲な陽の下を、今にも燃えそうな、乾いた草どもが意地悪く荷担するなか進めば進むほど、細かな短いうねりできみたちを灼く空気だ。
べとべとした暑さがきみたちのニューロンをねばつかせはじめると、もう手遅れだ。捕らわれた魂の盲目的な彷徨を短気な荒地から振り払うことはもうできない、そしてゆっくりと、とてもゆっくりと、多種多様な輪に対する嫌悪がとぐろを巻き、その地位を確固たるものにする、玉座の、あらゆる自己支配の玉座のど真ん中にて。
TGVアトランティックは、恐ろしいほどの効率で夜の中を滑るように進んでいた。照明は控えめだった。薄い灰色のプラスチックの壁面仕切りに囲まれて、人間たちはエルゴノミック・シートに身を横たえていた。彼らの顔には何の感情も表れていなかった。窓の方を向いても無意味だっただろう。闇の不透明さは絶対的だった。ちなみに、いくつかのカーテンは引かれており、その酸味がかった緑色は、カーペットの暗い灰色ともの悲しい調和を成していた。ほとんど絶対的なその静寂を乱すのは、ウォークマンから漏れるかすかな雑音だけだった。私のすぐ横の隣人は、目を閉じ、集中した無の状態へと引きこもっていた。唯一、トイレ、電話ボックス、そして「ケルベロス」と書かれたバーを示すピクトグラムの光の戯れだけが、その車両に生きた存在がいることを明かしていた。その車両には60人の人間が集まっていた。
細長く流線型で、控えめな色のストライプが入った鋼鉄製の灰色のTGVアトランティック6557号は、23両の車両を持っていた。1500人から2000人の人々が乗り込んでいた。私たちは西洋世界の果てへ向かって時速300キロで突き進んでいた。そして突然、私はある感覚に襲われた(私たちは夜を柔らかな沈黙に囲まれて進んでおり、その驚異的な速度を感じさせるものは何もなかった。ネオンの光の照明は力は弱く、葬儀のような青ざめた光だった)、私が突如抱いた感覚とは、この長い鋼鉄の船は私たちを運んでいる(控えめに、効率的に、そして優雅に)のであり、それは闇の王国へ、死の影の谷の方角へなのだというものだった。
10分後、私たちはオレーに到着した。